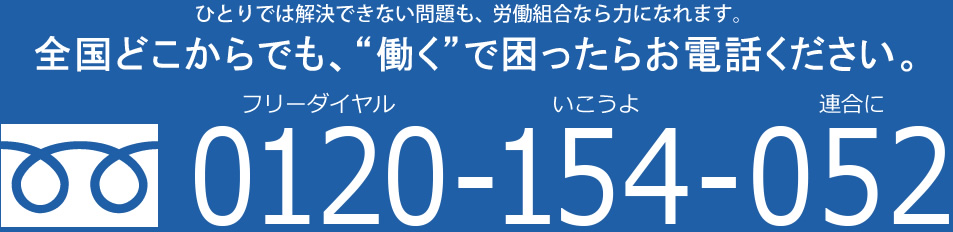連合の平和4行動のスタートとなる「平和行動in沖縄」が、6月23日(月)~24日(火)にかけて開催され、連合山口からは伊藤会長をはじめ構成組織・女性委員会および二つの地域協議会より青年委員会役員を含む16名が参加しました。
沖縄慰霊の日である6月23日には、那覇文化芸術劇場なはーとにおいて「連合2025平和オキナワ集会」が開催されました。
 第1部は、「新たな安全保障を目指して」をテーマに屋良朝博衆議院議員より基調講演がありました。安全保障ってなに?から始まり、安全保障の概念には普遍的な定義がないことや、今の私たちの世界観や価値観、時代背景や国の状況によっても意味あいが全く変わってくることについて説明を受けました。さらに現在の沖縄の状況や日米軍事訓練にも触れ、安全保障の手段は軍事的抑止力だけではなく、外交・地域理解・人的交流など多様であること、特に近年では、リーディング・ミドル・パワーとして他国の人道支援活動や災害救援活動、学校などの修復を展開していることなどの報告がされ、災害復旧や救援を通じた国際協力の輪が新たな安全保障のネットワークの構築につながる可能性があると示唆されました。
第1部は、「新たな安全保障を目指して」をテーマに屋良朝博衆議院議員より基調講演がありました。安全保障ってなに?から始まり、安全保障の概念には普遍的な定義がないことや、今の私たちの世界観や価値観、時代背景や国の状況によっても意味あいが全く変わってくることについて説明を受けました。さらに現在の沖縄の状況や日米軍事訓練にも触れ、安全保障の手段は軍事的抑止力だけではなく、外交・地域理解・人的交流など多様であること、特に近年では、リーディング・ミドル・パワーとして他国の人道支援活動や災害救援活動、学校などの修復を展開していることなどの報告がされ、災害復旧や救援を通じた国際協力の輪が新たな安全保障のネットワークの構築につながる可能性があると示唆されました。
第2部の平和式典の冒頭、沖縄戦や世界中で起きている戦争や紛争で犠牲になった方々のご冥福を祈り、参加者全員で黙とうを行いました。
 その後、主催者を代表して、清水秀行連合事務局長や連合沖縄の仲宗根哲会長から、過去の悲惨な戦争の状況や自らの母親の戦争体験やその事に対する想い、今の世界や日本・沖縄の状況に触れながら、戦後80年を経て、これからも平和への願いをつないでいくことについての挨拶がされ、次の平和行動の開催地である広島・大野真人連合広島会長へ「ピースフラッグ」が引き継がれました。
その後、主催者を代表して、清水秀行連合事務局長や連合沖縄の仲宗根哲会長から、過去の悲惨な戦争の状況や自らの母親の戦争体験やその事に対する想い、今の世界や日本・沖縄の状況に触れながら、戦後80年を経て、これからも平和への願いをつないでいくことについての挨拶がされ、次の平和行動の開催地である広島・大野真人連合広島会長へ「ピースフラッグ」が引き継がれました。
最後に、918名の参加者全員で「これからも、粘り強く、平和を求める行動を歩み続けていく」という「平和アピール」を確認し、平和オキナワ集会を終了しました。
翌24日のピースフィールドワーク(現地視察)では、基地コース~瀬嵩の浜(辺野古キャンプシュワブ)や道の駅かでな(嘉手納飛行場)、チビチリガマ(集団自決の地)、嘉数高台(中部戦跡、普天間飛行場)など、連合沖縄青年委員会を中心に構成組織から派遣された「ピースガイド」の説明を受けながら視察をしました。
また、終了後は、県庁前の広場に結集して、「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」を求める集会を開催し、7年ぶりとなるデモ行進を炎天下の国際通りで行いました。
≪2025平和行動in沖縄 参加レポート≫
【JR連合 日浦弘毅】
「2025 平和行動 in 沖縄」に初めて参加させていただき、普天間・嘉手納・辺野古の基地問題に触れ、また嘉数の高台やチビチリガマを訪れる中で、戦争の悲惨さと命の尊さをあらためて実感しました。
戦後80年という節目にあたり、多くの尊い命が奪われた事実を肌で感じ、平和の大切さを次世代へ語り継ぐ必要性を痛感しています。
連合沖縄の方々から直接伺った言葉には重みがあり、今なお続く過重な基地負担や理不尽な日米地位協定の問題に対し、私たちも決して無関心であってはならないと強く感じました。
沖縄慰霊の日に行ったデモ行進では、全国から集まった仲間とともに平和を願う声をひとつにしました。
今回の平和学習で学べた事や体験した事を共有すると共に、仲間と連携し労働組合の立場からも平和で公正な社会の実現に向け、争いの無い世の中を次世代へ継承すべく考動し続けていきたいと思います。
【JP労組 河村里美(連合山口女性委員会)】
今回、初めて平和行動in沖縄に参加させていただき、戦争のこと基地問題のことを学びました。
ピースフィールドワークでは、瀬嵩の浜から辺野古キャンプシュワブ、道の駅かでなから嘉手納飛行場、読谷村の集団死の地チビチリガマ、嘉数高台から普天間基地の視察をしました。
80年前の沖縄で起こった悲惨な出来事。
暗闇のガマでの恐怖との闘い、自分の大事な人や子を手にかけるということを想像して胸が締め付けられる想いでした。
戦争から80年経ったいま、沖縄で起こっている基地問題。
騒音を実際に肌で感じ、事件や事故が起こったときのことやその時の米軍の対応等を沖縄のガイドの方に聞き、戦後80年経ったいまでも戦争に苦しめられているという現実を他人事としてではなく自分ごととして捉えて考えていかなければいけないと感じました。
今回参加して改めて平和の重要性について学ぶことができ、戦争という悲劇を二度と繰り返してはいけないということ、犠牲になった方々の想いを忘れてはいけないということを次世代の子供たちに繋いでいくことが、いま私たちに出来ることなのではないかと思います。
また、私たちがいま当たり前に生活できていることの感謝のおもいを忘れずに生きていかなければいけないと強く思いました。
【情報労連 末満さゆり(連合山口女性委員会)】
私は今回、初めて平和行動in沖縄に参加しました。広島や長崎とは異なり、沖縄は地上戦が行われた地である。そのため、沖縄戦の悲惨さと現在も続く基地問題について深く学び、平和の尊さを感じました。
平和オキナワ集会では、安全保障についての講演があり「安全保障」という言葉に明確な定義がないことを初めて知り、これまで当然のように使われている言葉の曖昧さに驚きました。
ピースフィールドワークでは、辺野古基地、嘉手納基地、チビチリガマ、嘉数高台を巡りました。基地周辺では、平和な日常の中に軍事施設が存在する複雑な現実を実感しました。チビチリガマでは戦争の残酷さを深く感じ、嘉数高台からは激戦地を一望し、教科書で学んだ歴史がより身近に感じられました。
今回の平和行動を通して、平和は当たり前に存在するものではなく、一人ひとりが意識し、守り続けなければならないものだと痛感しました。沖縄の人々が今でも基地問題と向き合い続けている現実を目の当たりにし、平和の実現がいかに困難かを実感しました。今後は、この経験を周りの人々に伝え、平和について考え続けたいと思いました。
【県央地協 田中健太郎】
2025年6月22日から24日にかけて、連合平和行動in沖縄に参加しました。
訪れた地の中で最も印象的だったのはチビチリガマでした。この地では、当時米軍に捕まることを恐れ、家族同士で集団自決が行われており、今でもガマ(避難壕)の中には遺骨が眠っています。実際には米軍に捕まった近くのガマの方々は生還していますが、当時は米軍に捕まると恐ろしい目に合うとの情報が流されており、チビチリガマに逃げ込んだ方々は究極の選択として集団自決を選ばれたのだと思います。戦争という極限の状態で、家族を手にかける決断をせざるを得ない状況を考えると、胸が締め付けられる思いでした。
現在では観光地としての側面の強い沖縄ですが、80年前には実際にそのようなことが起こっており、多くの尊い命が失われています。
戦争は悲しみや後悔しか生みません。今回の平和行動を機に、戦争は二度と繰り返してはならないと強く心に刻むとともに、平和の尊さを改めて感じることができました。
【県央地協 吉富葉子】
このたび、平和行動に参加させていただきました。
今回の参加は、以前訪れた長崎に続き、私にとって2度目の平和行動となります。
特に印象に残ったのは、旧海軍司令部壕とピースフィールドワークで訪れたチビチリガマの視察です。
旧海軍司令部壕では、当時のまま残された壕の中に入ると、うす暗く湿った狭い空間の中で当時、約4,000人もの人が収容されており、最後には手榴弾で自決されたという事実を目の当たりにしました。壁に残る手榴弾の跡やひんやりとした空気が、当時の緊迫した状況を物語っているようで、強い衝撃を受けました。
チビチリガマでは、近くにもう1つガマ(自然洞窟)があり、そちらに避難していた人々の中に英語を話せる方が2人いたので、米兵と交渉することができたため全員が命を落とさずに済んだという話をピースガイドの方から伺いました。同じような状況に置かれながらもわずかな違いが生死を分けたという事実に居たたまれない気持ちになりました。
チビチリガマの前に建てられた慰霊碑には、わずか3歳の子どもの名前も刻まれており、幼いわが子を両親が自ら手にかけなければならなかった状況を想像するだけで、胸が苦しくなりました。このような悲劇が現実に起きていたという事実を、私たちは知る責任があり、そして決して忘れてはならないと強く感じました。
これまで沖縄戦については、資料やテレビ等で目にしたことはありましたが、今回の平和行動で現地を実際に訪れ、自分の目で見て、悲惨な戦跡を肌で感じることで、教科書や映像では得られない深い学びを得ることができました。
平和の尊さ、命の重みを改めて心に刻むことができた、非常に貴重な体験でした。
このような機会をいただき、本当にありがとうございました。
【県央地協 藤井奎輔】
今回沖縄戦に関連する史跡や米軍基地に初めて行くことができました。
旧海軍司令部壕の一部には、手りゅう弾で自決した弾痕が壁に残っていたり、チビチリガマの集団自決はどんな思いで家族の命を奪ったのかを考えるとものすごく胸が締め付けられるような感情になりました。時代や思想が人の人生をここまで変えてしまうのかと悲しい気持ちになりました。それと同時に、今日本が平和であることがどれだけ幸せなのかを実感しました。
話題の辺野古移設が着々と進んでおり、厳重に警備されていました。
詳しい事情は分かりませんが、辺野古移設で全てが丸く収まるのか疑問が残りました。
危険な飛行場といわれる普天間基地が住宅街にどれだけ近いのかを展望台から確認することができました。こんなことが許されている現状に少し憤りを感じました。私以上に現地の方々は先祖代々の土地を追い出されただけでなく、飛行機の墜落、騒音問題にも悩まされ不安やストレスは相当なものだと思います。在日米軍基地があることの重要性、恩恵を否定はしませんが、一緒の敗戦国であるドイツとアメリカの地位の関係性と比べると、この現状を黙認できません。
この平和行動in沖縄では、沖縄戦の悲惨さを知るだけでなく、終戦後も負担を強いられている現状を目の当たりにしました。連合などのあらゆる組織が一丸となって行ったデモは沖縄県民の声を代弁するかのようですごく意味のあることだったと思います。
これから少しでも基地についての進展があればいいなと思いました。
【県央地協 大河原深愛】
終戦80年目という節目に参加した沖縄平和行動は、私にとって2回目となるものでした。
1日目の平和オキナワ集会では、労働者の仲間である参加者918名と平和の尊さと戦争の悲惨さについて再認識することができました。
2日目の平和ピースフィールドワークで現地の銃弾の跡やガマを目の当たりにした時は、息が詰まってしまいました。その瞬間に感じた戦争に対する憤りや悲しみを、決して忘れることがないよう胸に刻み続けたいと思います。また、日本にある米軍基地の7割を占めている沖縄県の方だからこそお聞きできるお話が沢山あり、大変勉強になりました。今回の平和行動で初めて見学する基地やガマもあり、自分自身の「戦争と平和」についての知識をアップデートすることができました。改めて、このような貴重な機会をいただきありがとうございました。
戦争を知らない世代と言われる私たちですが、過去に日本でも戦争が起こっていたという事実から目を背ける訳にはいきません。このように過去を学んだからこそ、未来へ伝えていく責任があると思います。「平和」に関心を持ち続けること、資料館などに足を運ぶこと、沖縄平和行動で学んだことを発信すること、政治に参加すること、私に出来る小さなことを精一杯取り組みたいと強く感じました。
世界では今もなお紛争が起こっています。今この瞬間も、どこかで怯えている人がいると思うと、心苦しい気持ちでいっぱいです。どうか、1日でも早くこの世界中に平和が訪れることを願っています。